「遺言書を残しておけば安心」と思っていませんか?
確かに遺言書は相続をスムーズにするための強力な手段です。
しかし、実際には
- 遺言書の内容が有効か無効か争われるケース
- 遺留分の請求によって相続トラブルに発展するケース
が後を絶ちません。
この記事では、遺言書があった場合の相続手続きの流れ、有効・無効の判断基準、遺留分侵害額請求のリスクと回避法をわかりやすく解説していきます。
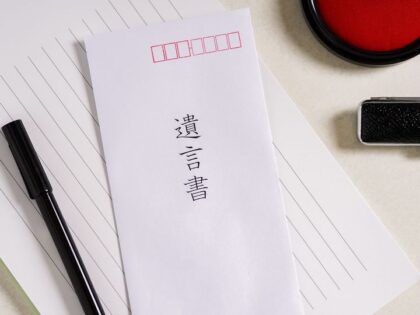
遺言書があった場合の相続手続の基本
遺言書があると相続はどう変わる?
日本の相続制度では、本来「法定相続分」に基づいて財産を分けます。
しかし、遺言書が存在する場合はその内容が優先されます。
たとえば「自宅は妻に相続させる」と遺言書に書かれていれば、他の相続人が異を唱えても基本的には妻が相続できるのです。
遺言書の種類と特徴
遺言書には大きく3種類があります。
- 自筆証書遺言: 自分で全文を書く。手軽だが不備で無効化されやすい。
- 公正証書遺言: 公証人が作成。最も安全で確実。
- 秘密証書遺言: 自作したものを封印し、公証人に手続きしてもらう。実務上は少ない。
特に安心できるのは公正証書遺言で、裁判所を通さずにすぐ手続きができ、紛失や改ざんの心配もありません。
遺言書が有効か無効かの判断基準
遺言書は、作ったからといって必ずしもすべて有効とは限りません。
無効になる代表例
- 日付や署名・押印がない
- パソコンで作った(自筆証書遺言の場合)
- 認知症などで判断能力がなかった
- 財産の指定があいまい(例:「長男に土地をやる」だがどの土地か不明)
有効とされる条件
- 法律で定められた方式を守っている
- 遺言者に意思能力があった
- 財産の対象が明確に特定できる
👉 遺言書が無効とされると結局「法定相続」に戻ってしまい、家族の意向とズレが生じる可能性があります。
有効な遺言書でも発生する「遺留分」の問題
遺留分とは、法律で保障された最低限の取り分のことです。
「全財産を長男に渡す」といった遺言があっても、他の相続人には遺留分が認められています。
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人 (父・母のみが相続人の場合など)→ 遺産の3分の1
- それ以外(配偶者・子がいる場合) → 遺産の2分の1
この権利を侵害する遺言があれば、相続人は遺留分侵害額請求を行使できます。
遺留分侵害額請求が行使されるとどうなる?
トラブルの実例
- 長男に家を残す遺言 → 次男が遺留分を請求 → 長男が遺留分に相当する現金を払えず結局家を売却
- 「父は俺に任せると言ったのに!」と兄弟間で口論に
- 裁判や調停に発展し、相続が長期化
👉 遺留分を考慮しない遺言は、かえって家族の仲を壊してしまうリスクが高いのです。
遺言書をめぐる相続トラブルを防ぐ方法とは
では、どうすれば遺言書をめぐるトラブルを防げるのでしょうか?
1.公正証書遺言を作る
形式不備を防ぎ、安心して残せる。
2.遺留分を考慮する
特定の人に偏らないよう分配を工夫する。
3.生前贈与や保険を活用する
相続開始前に財産を整理し、遺留分請求に備える。
4.家族に説明しておく
「なぜこのような遺言にしたか」を元気なうちに伝えておくことが最大の防止策。
遺言書は「財産分け」ではなく「家族の未来を守る手紙」
遺言書は相続手続きの際に、強力な道しるべになります。
ただ、無効化のリスクや遺留分トラブルの恐れもあり、遺言書作成者本人の気持ちだけでなく、遺された家族の気持ちや遺留分への理解が足りないと、さらにトラブルが泥沼化してしまう可能性も。
有効な遺言書と家族の理解があってこそ遺言書を作成することには大きな意味があるのです。
遺言書は単なる財産分けの書類ではなく、遺された家族に「どう生きてほしいか」を伝える最後のメッセージでもあります。
相続争いを避け、家族の未来を守るために、今のうちに「正しい遺言書」を考えてみてはいかがでしょうか?



