「相続税は高い」と耳にしたことがある方は多いと思います。
では、どうすれば少しでも負担を軽くできるのでしょうか。
よく使われる方法のひとつが「生前贈与」です。つまり、財産を生きているうちに子や孫に移してしまうのです。
ところが、ここで出てくるのが 贈与税 というもうひとつの税金。
「贈与税は相続税より税率が高い」と聞いて怖くなり、結局何も対策しないまま相続を迎えてしまうケースも少なくありません。
実は、この「相続税」と「贈与税」の間には仕組み上の差(乖離)があり、それをうまく利用すれば節税につながるのです。
今回は、2024年(令和6年)の改正で新しく追加された「110万円の基礎控除」を含む 相続時精算課税制度 を利用した事例を使って、わかりやすく解説していきます。
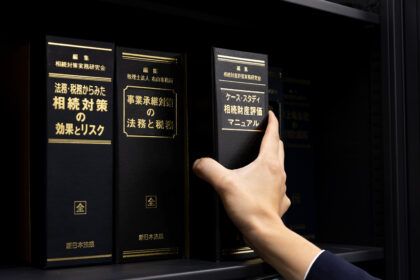
まずは基本を整理しましょう
相続や贈与の税金の仕組みは大きく2種類に分かれます。
① 暦年課税(れきねんかぜい)
- 毎年110万円までの贈与は非課税
- ただし、相続開始前3年以内(2027年以降は7年)の贈与は相続財産に戻される(持ち戻し)
- 少しずつコツコツと贈与する人が多い
② 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
- 毎年110万円の基礎控除がある(2024年改正で新設)※
- さらに贈与者(贈与する人)ごとに累計2,500万円までの特別控除
- 超えた部分は一律20%の贈与税
- 相続時には贈与財産を合算して精算するが、評価額は「贈与した時の価格」で固定
この「価格を固定できる」という特徴こそが、大きな節税効果を生むカギになります。
※2024年から、相続時精算課税にも 暦年贈与と同じ110万円の基礎控除 が導入されました。
これにより、精算課税を選んでも毎年110万円分の贈与は相続財産に戻さなくてよい、という扱いになります。
つまり「毎年110万円を安心して贈与できる」だけでなく、将来値上がりする資産についても「評価を固定できる」メリットが併せて使えるようになったのです。
次に具体例でみてみましょう
- 父の総財産:1億5,000万円(現金1億円+収益不動産5,000万円)
- 相続人:妻1人・子2人
- 相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円 の場合
【生前贈与をせずにそのまま相続した場合】
遺産総額の1億5,000万円から基礎控除の4,800万円をマイナスするので、
・課税遺産総額:1億5,000万円-4,800万円=1億200万円
よって、相続税総額(概算)は約1,500万円となります。
【収益不動産5,000万円を精算課税で長男へ贈与した場合】
- 贈与時の評価:5,000万円
- 控除適用:110万円+特別控除2,500万円=2,610万円
- 課税価格:5,000万円-2,610万円=2,390万円
- 贈与税:2,390万円×20%=478万円(相続税から控除可能)
その後、相続時には
- 父の残り財産:1億円
- 加算される贈与財産:5,000万円-110万円=4,890万円
- 合計:1億4,890万円
- 課税遺産総額:1億4,890万円-4,800万円=1億90万円
よって、相続税総額(概算)は約1,500万円(既に納めた478万円は控除)
一見すると税額は変わりません。では、どこにメリットがあるのでしょうか?
ここで、注目すべき点は、5,000万円が収益不動産であることです!
精算課税を利用して贈与した際には5,000万円だった不動産が、実際に相続が発生した20年後には7,500万円に評価が上がっていた場合、
- 精算課税を使っていれば、相続時に加算されるのは 贈与時評価の4,890万円 で固定
- 値上がり分の2,500万円は課税対象外
- 相続税率を30%とすると、750万円もの節税効果に
さらに、贈与した時点から不動産の収益は子のものになります。つまり、相続開始までに得られる家賃収入なども父の財産に含まれないのです。
収益不動産だけでなく、非上場株式でも効果は大きい
非上場株式は将来の成長次第で大きく値上がりする可能性があります。
- 贈与時評価:2,500万円
- 20年後に5,000万円へ成長
- 相続時に加算されるのは贈与時の2,390万円(2,500万円-110万円)
- 成長分2,500万円は課税対象外 → 相続税750万円程度を節税
株式の成長益をまるごと切り離せる点では、不動産以上に効果的な場合もあります。
相続税と贈与税の「乖離差」を活かすポイント
- 現金贈与よりも値上がり資産贈与が有効
現金は価値が変わらないため効果が限定的。値上がり資産こそ精算課税の真価を発揮します。※値上がりを見込んで贈与したのに、もし下落すれば逆効果になる可能性もあります。
- 110万円基礎控除の活用
精算課税を選んでも、毎年110万円分は相続に持ち戻ししません。安心してコツコツ移せます。 - 暦年贈与と使い分け
他の相続人へは暦年贈与で少額を移転。値上がり資産は精算課税でまとめて移転。この併用が合理的です。
ただし、精算課税の選択は一度行うと取り消すことができません。贈与者ごとに一度きりの選択なので慎重に行いましょう。
また、贈与したことを明確にするため、贈与契約書や資産評価の根拠をきちんと残しておくことが大切です。
まとめ
- 相続税と贈与税には制度上の「差」があり、その仕組みを理解して使い分けることで節税につながります。
- 特に2024年改正で、相続時精算課税に「毎年110万円の基礎控除」が導入されたことにより、戦略の幅が広がりました。
- 現金よりも将来値上がりする資産(収益不動産や非上場株式)に精算課税を使うことが効果的 です。
- 暦年贈与と精算課税を組み合わせることで、相続税対策はさらに合理的に進められます。
大切なのは「思い立った時に動く」こと。
値上がり資産を抱えている方にとって、この制度改正は大きなチャンスです。早めに専門家と相談し、自分に合った戦略を立てていきましょう。



