今回は、「同族会社の死亡退職金」について、よくいただくご相談をもとにお話しします。
会社を経営している方にとって、ご自身に万が一のことがあったときの「退職金」をどう取り扱うのかは、法人税・相続税の両面でとても大事なポイントです。
さらに、不動産賃貸業などを事業的規模で営んでいる方には、「小規模企業共済」を死亡退職金代わりに活用できる制度もあります。
どのように取り扱うことがご自身には一番合っているのかをぜひ検討してみてください。
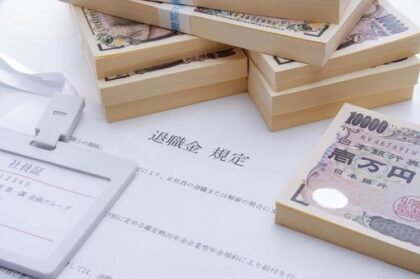
死亡退職金とは?
役員や従業員が退職する際に会社から支給されるのが「退職金」です。
経営者ご本人(例えばオーナー社長)が亡くなったときも、会社から「死亡退職金」という名目で遺族に支給できます。
これは会社にとっては「損金」(経費のような扱い)になり、法人税の負担を減らすことができます。
一方で、受け取った遺族にとっては「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税には「死亡退職金の非課税枠」というものがあり、
500万円 × 法定相続人の数 まで非課税で受け取れるメリットがあります。
例えば、法定相続人が妻と子2人の合計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税 です。
つまり、うまく設計すれば、会社のお金を相続税の負担を少なくしながらご家族に遺せるわけです。
いくら支給してもいいの?税務署の判断基準
ここで気になるのは、「退職金をいくらに設定すればよいのか」という点です。
極端に高い金額を設定すれば、法人税を減らすための不自然な操作だと税務署に見られてしまいます。
税務署が目安として使うのが「功績倍率法」という考え方です。
計算式はシンプルで、
退職金額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
例えば、社長の最終報酬が月100万円、勤続30年、功績倍率3倍とすると、
100万円 × 30年 × 3倍 = 9,000万円 が妥当とされます。
では功績倍率はどのくらいが一般的かというと、
- 一般取締役:1~2倍
- 代表取締役(社長など):3倍程度
- 特別に功績が大きい場合:3倍超も認められるケースあり
この範囲を大きく外れると、税務署から「一部は損金として認めません」と否認される可能性があります。
つまり、退職金を決めるときは「自分の勤続年数・役職・報酬水準」といった客観的な根拠が大切になるのです。
会社としての手続き(会社法上のルール)
「会社のお金を家族に遺すのだから、好きなように決めていいのでは?」と思われがちですが、実はそうではありません。
会社法では、役員に退職金を支給する場合、株主総会の決議 が必要です。
特に同族会社の場合は、あらかじめ「退職慰労金規程」を作っておくことが実務上は安心です。
規程や株主総会で「退職慰労金を支給する」と決め、そのうえで具体的な金額を取締役会や代表取締役が決定する流れが一般的です。
こうしておけば、税務署に対しても「適正な手続きを経て支給した退職金です」と説明しやすくなります。
受取人は誰になるの?
もうひとつ大事なのが「誰が死亡退職金を受け取るのか」という点です。
- 会社が規程や決議で「遺族に支給する」と指定している場合 → その受取人が権利を持ちます。
- 特に指定がない場合 → 法律上は「相続財産」として、相続人全員の共有財産となります。
つまり、遺族間で揉めないためには、会社の退職慰労金規程や株主総会で「受取人」をはっきり決めておくことが大切です。
さらに、受取人を複数に分けておけば、先ほどの「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠をフル活用できます。
例えば、妻だけが受け取るのではなく、妻・子・子の3人で分けることで非課税枠を1,500万円に拡大できるのです。
不動産オーナーは「小規模企業共済」で死亡退職金を準備できる
ここで不動産賃貸業を事業的規模(いわゆるアパート10室以上や駐車場50台以上など)の規模で営んでいる方にも朗報です。
実は「小規模企業共済」という制度を利用すれば、経営者や個人事業主も「退職金」を自分で積み立てることができます。
- 掛金は全額所得控除(節税になる)
- 事業をやめたときや死亡時に「退職金」や「遺族退職金」として共済金を受け取れる
- 受け取った遺族退職金は相続税法上「みなし相続財産」となり、死亡退職金と同様に500万円 × 法定相続人の非課税枠が適用される
つまり、会社を持っていない不動産オーナーでも「自分の死亡退職金」を準備できるわけです。
これは知らない方が多いのですが、とても有効な相続対策になります。
| 死亡退職金は「法人税の節税」と「相続税の非課税枠」という2つのメリットがある |
| 金額は「最終報酬×勤続年数×功績倍率」が目安。代表取締役なら3~4倍が一般的 |
| 支給には会社法上の手続(株主総会決議)が必要。受取人も規定で定めておくと安心 |
| 受取人を複数にすることで「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を最大限に活用できる |
| 不動産賃貸業を事業的規模で営む方は「小規模企業共済」で自分の死亡退職金を準備できる |
経営者や不動産オーナーの方にとって、死亡退職金は「会社のお金や自分の積立を、最も有利にご家族に渡す方法」のひとつです。
ただし、金額の設定や手続きが不十分だと、税務署から否認されたり、家族間でトラブルになったりするリスクもあります。
「うちの会社ではいくらぐらいが妥当なのか?」「退職金規程はどう整備すればいいのか?」
こうした点は個別事情によって変わりますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。



